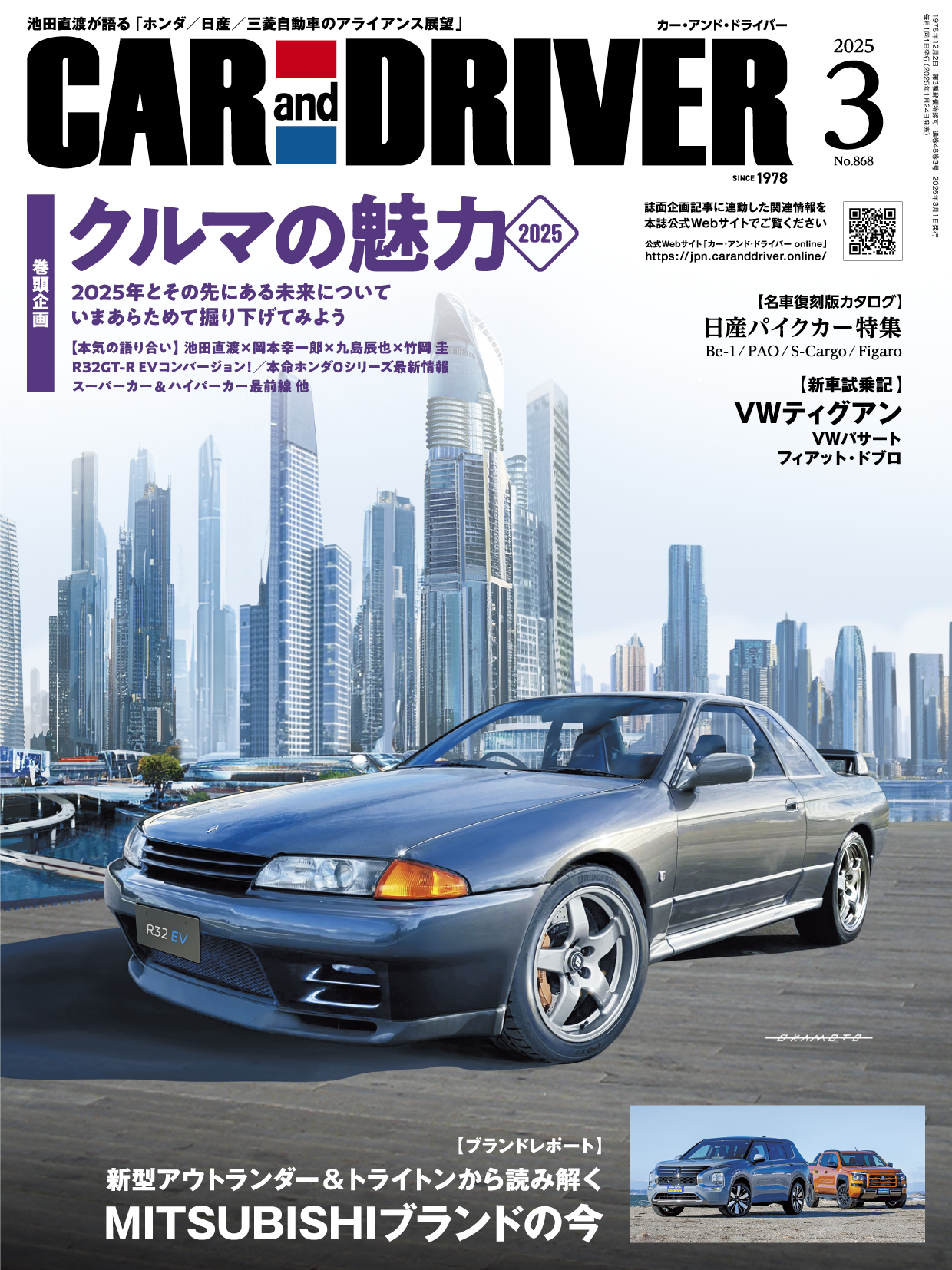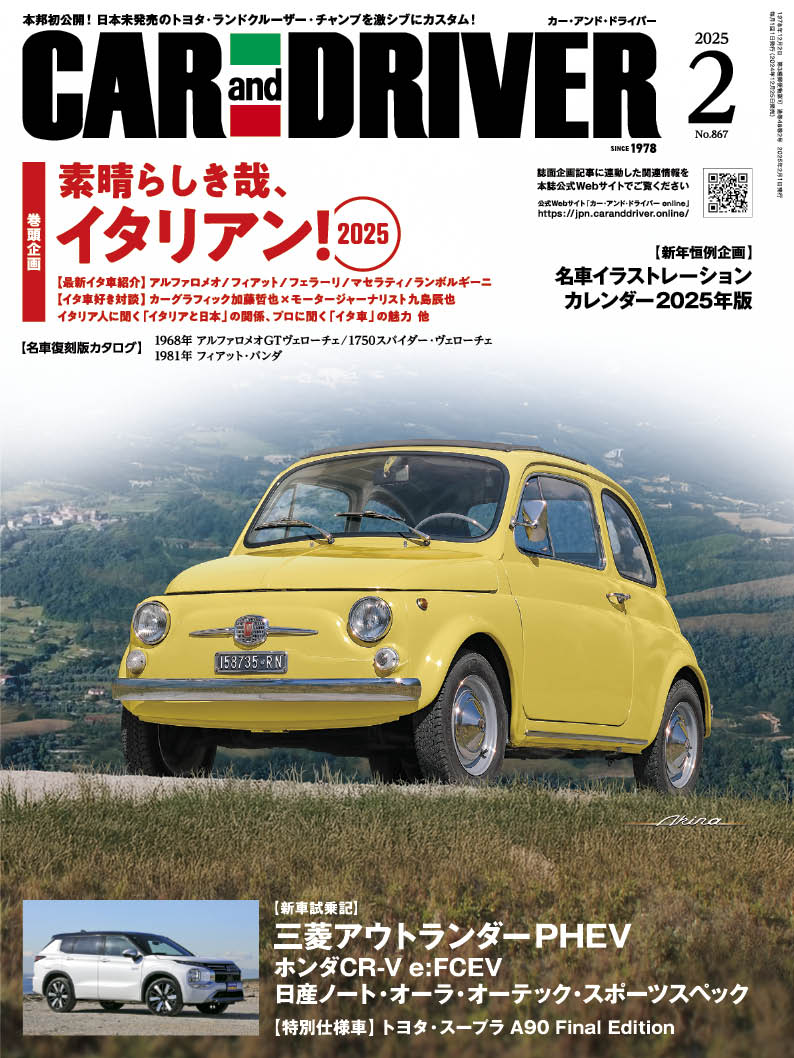Ado、tuki.、yama など若い世代を中心に顔出しNGのアーティストが増加中
若い世代を中心に人気が高いアーティスト、Ado、tuki.、yama、なとり、ヨルシカ、コレサワ……彼らに共通していること。それは顔出しをNGにしていることだ。
以前から、人気アーティストのGReeeeN、MAN WITH A MISSIONなどが顔出しをNGとしていたが、最近、顔出しをNGにするアーティストが増えてきている。彼らはなぜ顔出しNGなのだろうか。それぞれ独自の理由があると思われるが、増加の背景には最近の音楽業界の変化が大きく影響をしている。
現代の価値観に沿って音楽業界が変化
アーティストの顔出しは、必須ではなくなった
音楽業界の変化、そこにはまずプロモーションの変化が挙げられる。大きいのはSNSの普及だ。インターネット、とりわけSNSがなかった時代は、アーティスト名や楽曲の主なプロモーション手段は、TVなどのメディアへの出演、ライブ活動だった。一方、現在はSNSで話題になり、情報が拡散されることが重要になっている。読者の中には、マスメディア主体のプロモーションに馴れているので、「顔が出ていないミュージックビデオに違和感がある」という人がいるかもしれない。だが、YouTubeやTikTokでは楽曲そのものを評価して人気が出るケースが多く、今日の若い世代は、顔が見えないアーティストを違和感なく受け入れる、というよりそれが普通の状態でもある。アーティストが自らの姿を見せる必要性が薄くなってきているのだ。
またSNSが普及し、誰かが誰かの楽曲を気に入って、“歌ってみた”や“踊ってみた”で使用し、これがヒット・再生回数の増加につながるケースが珍しくない。また、楽曲を生み出す新たな方法として、ボカロP+歌い手という組み合わせが一般化してきている。ボカロPとは、自らが作成した楽曲にボーカロイドなどの音声合成ソフトを用い人工的な歌声をのせ楽曲を発表する人のことだ。歌い手とは、SNSで既存の楽曲のカバーやボカロPが発表した楽曲を歌い発表する人。現在は、SNS上でボカロPと歌い手が出合い楽曲を発表する、もしくはレコード会社などがボカロPと歌い手をマッチングさせ、楽曲を発表するというケースが増え、ここからヒット曲が数多く生まれている。
このボカロPや歌い手にとって、顔を出すことは大きな意味を持っていない。多くの場合、それぞれの目的がボカロPは楽曲を発表する事、歌い手は歌唱を披露することだからだ。こうして整理すると、オリジナルの楽曲を制作したアーティストの顔が見える・顔が見えないという活動スタイルと、ヒットの関連性が薄れてきている現状がわかる。
思い返せば、米津玄師もYOASOBIのAyaseもボカロP時代には顔を出していなかったし、Adoやyamaは歌い手として登場したいまも顔を出していない。ヒット曲を生み出すうえで、顔出しをする必要がもはや必須ではないのだ。
顔出しなしでもOKになって
アーティストになる道は広がった
顔出しが必然でなくなった環境が整った結果、従来は、「恥ずかしい」「周囲に知られたくない」などの理由から、アーティスト活動をあきらめてきた才能豊かな人たちが、音楽業界に進出をするようになった。
実際、顔出しNGアーティストはどんなヒット曲を生み出しているのだろうか。
人気面で筆頭といえるのがAdoだろう。2020年『うっせえわ』でデビュー、2022年には劇場版アニメ、『ONE PIECE FILM RED』の劇中歌を担当、アルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』から、ビルボードジャパンのシングルチャートの上位10位に7曲が入るという快挙を成し遂げている。2024年12月には、グラミー賞受賞バンドのイマジン・ドラゴンズとコラボした『Take Me to the Beach feat. Ado』をリリースし、世界的ヒットを記録した。
2024年のNHK紅白歌合戦に出場したtuki.にも注目。2023年にリリースした『晩餐歌』がロングランヒット。ビルボードジャパンのシングルチャートで年間2位を獲得している。
顔の上半分を仮面で隠したyamaは、2020年のデビュー曲『春を告げる』がストリーミング累計再生回数が1億回を突破。『SPY×FAMILY』や『機動戦士ガンダム』、『るろうに剣心』などアニメ作の主題歌を数多く手がけ、ヒットとなっている。
2021年からTikTokで作品を発表するなとりは、『Overdose』『フライデーナイト』が共にストリーミング累計再生回数が1億回を突破。最新作の『糸電話』は映画『傲慢と善良』の主題歌となりZ世代を中心に人気の曲になっている。
生成AIの進化が日々話題となっている現在、顔出しが必然でないならば、実在の楽曲制作者&歌唱者が存在しないヒット曲が生まれる日もそう遠くはないだろう。カーステレオを聞きながら、アーティストのビジュアルをイメージしていたスタイルは、昭和〜平成のドライブといえるのだろうか。

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)