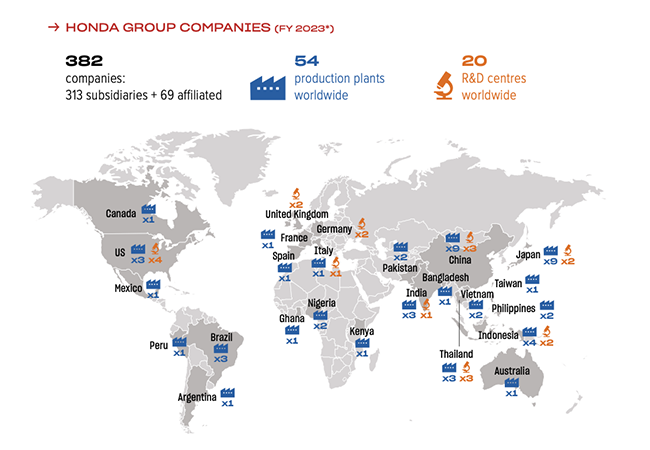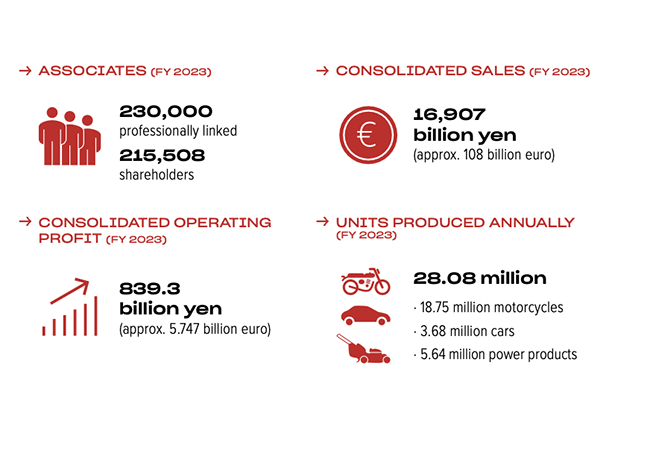【企業分析】ホンダの強さは、自由に発想し、個々人が信念をもって仕事をする企業文化にある。 過去の成功体験をとらわれない!

ホンダ三部社長は2024年5月の「2024ビジネスアップデート」会見で、2040年までに新車販売をすべてEV/FCEVとする目標を堅持したまま、現状ではハイブリッドをいっそう進化させ、エンジン開発も守ると表明。時代に即したパワーユニットで勝負すると宣言した
創業者、本田宗一郎の「夢」がすべての原点
本田宗一郎という、強烈な個性を持つ技術者が1948年に創業したホンダ(本田技研工業株式会社)。彼らが、これまで数々の独創的かつ先進的な製品を世に送り出してきたのは、他に例を見ない独自の気質を持ち続けてきたからだと私は捉えている。
中でも注目点は、ホンダの“人間尊重”という基本理念に掲げられた“自立”という項目。「既成概念にとらわれず自由に発想し、自らの信念にもとづき主体性を持って行動し、その結果について責任を持つこと」と記されている。
これこそ、ホンダが幾多の独創的な製品を生み出してきた、根本の思想といえるものではないか? ライバルたちの動向はどうでもいい。場合によっては社内の意向に背くことさえある。それよりも自らが自由に発想し、主体的に行動して製品を作り上げる。さらにいえば、ここに「技術の可能性を信じ、技術と真摯に向き合う姿勢」を付け加えると、ホンダが独創的かつ先進的な製品を開発し続けてきたこれまでの歴史を、すべて説明できる気がする。
つねに前を向く姿勢がホンダの伝統。ただし“過去を振り返る”ことも大切である
柔軟で主体的な開発思想を十二分に生かすため、ホンダのクルマ作りでは“プロジェクト制”が採用されてきた。これは、ひとつの製品を開発する際、エンジン/駆動系/ボディなどの各部署からプロジェクトに参加するメンバーを募り、彼らを中心とするタスクフォースを結成。製品開発の責任を負うLPL(ラージ・プロジェクト・リーダー)のリーダーシップのもと、特定の製品を開発するために各メンバーが全力を投じる体制を指す。
私が見たところ、LPLの権限は強大で、ときにはプラットフォームなどの共用技術さえ製品の個性や目的に合わせてモディファイする場合がある。私はこれを“機種優先の開発思想”と呼んでいる。プロジェクト制のおかげでひとつの製品として見たときの完成度は高く、他社の製品を上回る性能を発揮するケースが多い。
もうひとつの特徴が、“過去を振り返らない姿勢”である。ホンダの新製品説明会などに参加した際、「旧型車のこの部分はとてもよくできていたので、そのまま流用しました」という言葉を耳にする機会はめったにない。それよりも、改良の余地がないかと目を皿のようにして探し、改良点が見つかれば躊躇なくリファイン。製品の完成度と性能をさらに高めていくケースが、はるかに多い。
こうした、過去にとらわれない姿勢は、技術開発だけでなく企業文化の面でも目にする。たとえば、三部敏宏現社長は就任直後の2021年4月23日に行ったスピーチである。「2040年までにEV、FCVの販売比率をグローバルで100%を目指す」と宣言し、事実上、2040年までにエンジン車の生産を終了する方針を明らかにした。
この電動化戦略が正しいかどうかはさておき、もともとエンジン生産で創業したホンダである。“エンジンを捨て去る”という決断はなかなかできるものではない。しかし、過去にとらわれず、あくまでも未来志向で開発に取り組む姿勢こそが、数々の独創的製品を生み出す原動力となってきたことは間違いないだろう。
そして肝心の“エンジンを捨て去る”ことについても、公に発表されている方針とは微妙に異なる動きが社内にはあるようだ。たとえば、現在エンジン開発を担当しているホンダの技術者に話を聞くと「いまもエンジン開発に取り組んでいるし、将来的な方針が見直された場合に備えた準備もしている。それがエンジン開発担当としての責任」という主旨の答えが返ってくる。つまり、前述の“自立”の精神に則って、会社の方針とは別に「自らの信念にもとづき主体性を持って行動」しているのである。
彼らの“謀反”ともいうべき行動を、ホンダの上層部は承知しているはずだ。しかし、あえてそれを黙認し、その活動を認めているからこそ、開発に必要な予算も与えられているのだろう。私はここに、多様性を認めるホンダの、企業文化の奥深さを見る。
ホンダ社内の動きを“バラバラで統制がとれていない”と一刀両断にするのは簡単だ。けれども、“多様性を認める企業文化”をホンダが備えていなければ、カブやCB750、さらにはS500/600/800、N360、初代シビック、初代シティといった独創的な製品は生まれてこなかったに違いない。つまり、“多様性を認める企業文化”こそがホンダの宝物であり、独創性を育む土壌となっているのである。
もちろん、そこにはある種の課題も含まれている。あまりに多様性を容認し、LPLたちの“機種優先の思想”が極端に横行すれば、会社全体の開発効率が低下、経営を圧迫する事態にもなりかねない。数年前、ホンダの4輪事業はほとんど利益を生み出していない実情が取り沙汰された。こうした多様性を認める企業文化がその一因だったのかもしれない。
ただし、“過去を振り返らない姿勢”については、見直すべき時期に差し掛かっているような気がする。
ホンダは2023年、創業75周年を迎えた。彼らがこれまで世に送り出した製品を、その後も長く愛用し続けている顧客は少なくない。そういった顧客に感謝の意を示すためにも、歴史を重んじ、伝統を大切にする文化も一定程度は必要ではないか。たとえば、ひとつの車名、もしくはその開発思想を受け継いでいく姿勢は、長年ホンダ製品を愛用する顧客に感謝の思いを伝えることに結びつく。ひいてはビジネスの継続性を生み出して安定的な経営にも貢献すると考えられる。
ただし、そういった風潮が強くなりすぎると、ホンダの独自性や先進性は失われてしまう。要はバランスの問題である。これまで数々の革新的な製品を生み出してきたホンダであれば、難しい社内改革にもきっと成功するはず。それらを可能にする柔軟性やチャレンジ精神もまた、“ホンダの底力”と呼ぶべきものだろう。

![カー・アンド・ドライバーonline [CAR and DRIVER]](https://www.caranddriver.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/cdonline-logo.png)